
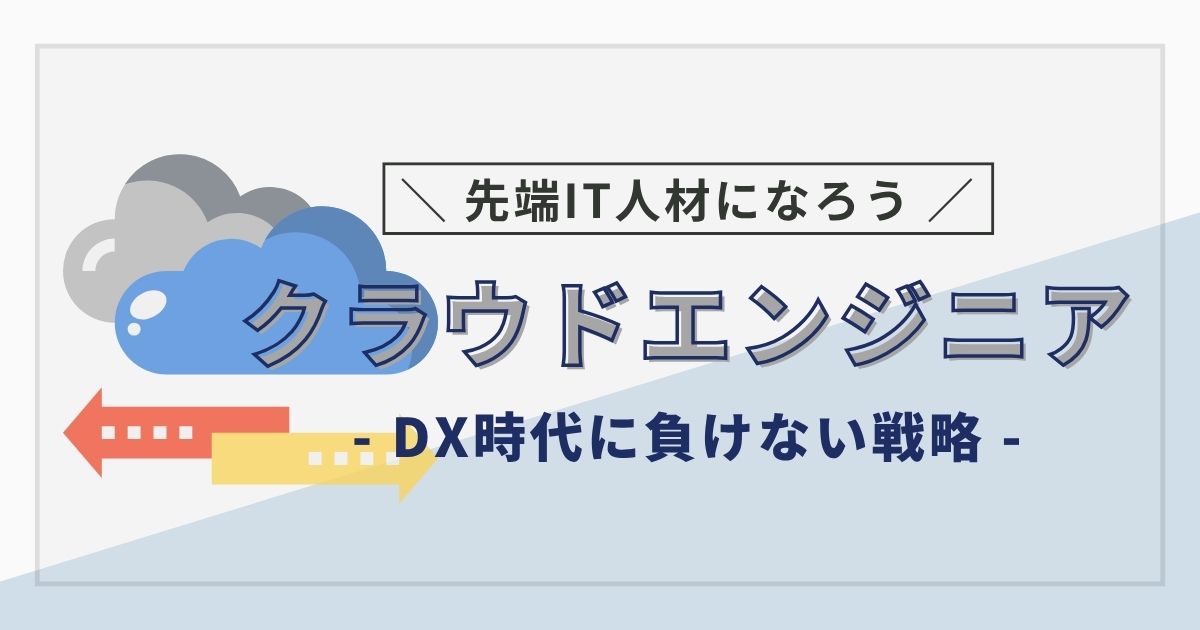
クラウドエンジニアとは、AWS・Azure・GCPなどのクラウドサービスを活用して、企業のITインフラの設計・構築・運用を担う専門職です。従来の物理サーバーを使ったオンプレミス環境とは異なり、インターネット上のクラウド環境でシステムを構築・管理することが主な業務となります。
なぜこれほど注目されているのでしょうか。企業のDX推進が加速している一方で、IT人材が最大79万人不足する事態に直面しており、特にクラウド技術者の不足は深刻な状況です。この需給ギャップこそが、未経験からでも高年収を目指せる大きなチャンスとなっています。
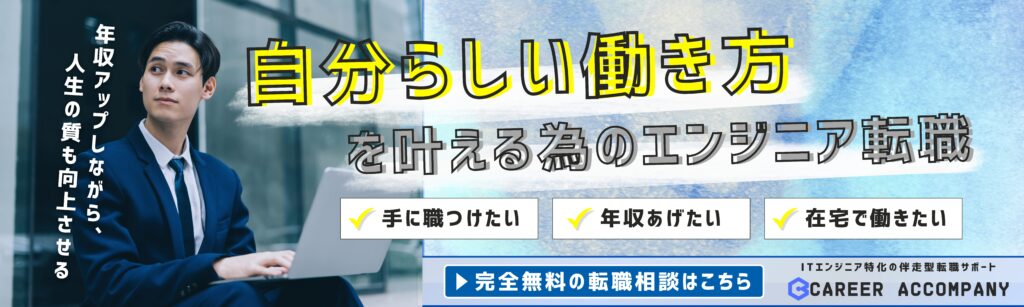

本当に今がクラウドエンジニアを目指すベストタイミングなの?
という疑問をお持ちの方も多いでしょう。結論から言うと、まさに今が絶好のチャンスです。その根拠を具体的な数字でご説明しましょう。
クラウド市場の成長が注目を集めています。日本のクラウドサービス市場は2024年に5兆円を超え、年平均成長率24.4%という力強い成長を続けています。総務省の情報通信白書によると、2023年のパブリッククラウドサービス市場は3兆1,355億円(前年比25.8%増)となっており、この業界の将来性の高さを物語っています。
しかし、この急成長に人材供給が全く追いついていません。経済産業省の調査では、2030年にIT人材が最大79万人不足すると予測されており、特にクラウドエンジニアを含む「先端IT人材」は現在でも約4.8万人が不足している深刻な状況です 。
この需給ギャップは年収面でも魅力的です。クラウドエンジニアの平均年収は約597万円とITエンジニア職種の中でも高水準です。企業のDX取組も加速しており、IPAの調査では取組企業の割合が2021年の55.8%から2023年の73.7%へと大幅に増加しています。


クラウドエンジニアって具体的にどんな仕事をするの?
と疑問をお持ちの方も多いでしょう。クラウドエンジニアの業務は多岐にわたりますが、主に4つの核となる業務があります。それぞれについて詳しく見ていきましょう。
クラウドエンジニアの最も重要な業務の一つが、クラウドインフラの設計・構築です。従来の物理サーバーを使ったオンプレミス環境とは異なり、AWS(Amazon Web Services)、Microsoft Azure、Google Cloud Platform(GCP)などのクラウドサービスを活用して、企業のニーズに最適なシステム基盤を設計します。
具体的には、企業の要件に応じてサーバーの規模やネットワーク構成を決定し、データベースやストレージの配置を設計します。例えば、ECサイトを運営する企業であれば、トラフィックの増減に自動で対応できる仕組みを構築したり、グローバル展開を見据えて複数リージョンにシステムを分散配置したりします。
この業務では、クラウドプラットフォームの特性を深く理解し、コスト効率と性能のバランスを取りながら最適な構成を提案する能力が求められます。IPA(情報処理推進機構)の調査によると、システム開発の内製化を進める企業が増加しており、特に従業員1,001人以上の企業では40.4%が内製化を進めています 。
システムを構築した後は、24時間365日の安定稼働を維持することが重要な業務となります。クラウドエンジニアはシステムの監視体制を構築し、障害の早期発見と迅速な対応を行います。
現代のビジネスではシステムの停止が企業の損失に直結するため、予防保守や自動復旧機能の実装が欠かせません。例えば、サーバーの負荷が高まった際に自動的にリソースを増強するオートスケーリング機能や、障害が発生した際に別のサーバーに処理を切り替えるフェイルオーバー機能を設定します。
同時に、クラウドのコスト最適化も重要な責務です。クラウドサービスは使った分だけ課金される従量制が基本のため、無駄なリソースの削減やより効率的なサービスへの切り替えを継続的に検討し、企業のコスト削減に貢献します。実際に、専門的な運用サービスを活用することで、Azure環境において月額コストを30%以上削減できた事例も報告されています。
関連記事:【保存版】監視業務とは|仕事内容・給料・楽きついの実態を全て公開
関連記事:【2025年版】システム運用保守とは?運用・保守の違いと監視経験を活かす方法
企業のDX推進において、既存のオンプレミスシステムをクラウドに移行する業務は非常に重要な役割を担います。多くの企業が自社のデータセンターで運用していたシステムをクラウドに移行することで、コスト削減や運用効率化を図ろうとしています。
IPAの調査では、企業のDX取組企業の割合が2021年の55.8%から2023年の73.7%へと大幅に増加しており、この流れに伴ってクラウド移行の需要も急速に高まっています。
クラウドエンジニアは、既存システムの現状分析から始めて、最適な移行戦略を策定します。全てを一度に移行するビッグバン方式ではなく、段階的に移行するフェーズドアプローチを採用することが多く、業務への影響を最小限に抑えながら移行を進めます。また、移行後の運用方法の見直しや、クラウドネイティブな機能の活用提案も行います。
クラウド環境でのセキュリティ対策は、従来のオンプレミス環境とは異なる専門知識が必要な領域です。クラウドエンジニアは、企業のデータとシステムを様々な脅威から守るため、包括的なセキュリティ対策を実装し、各種法規制やコンプライアンス要件に適合した環境を構築します。
具体的には、アクセス制御の設定、データの暗号化、ネットワークセキュリティの構築、ログ監視システムの実装などを行います。また、GDPR(一般データ保護規則)、HIPAA(医療保険の相互運用性と説明責任に関する法律)、PCI-DSS(クレジットカード業界のデータセキュリティ基準)など、業界特有の規制に対応した設定も重要な業務の一つです。
さらに、セキュリティインシデントが発生した際の対応計画の策定や、定期的なセキュリティ監査の実施、脆弱性評価とその対策も担当します。クラウドプロバイダーが提供するセキュリティ機能を適切に活用しながら、企業固有のセキュリティ要件に対応することが求められます。
これら4つの主要業務を通じて、クラウドエンジニアは企業のDX推進を技術面で支える重要な役割を果たしています。

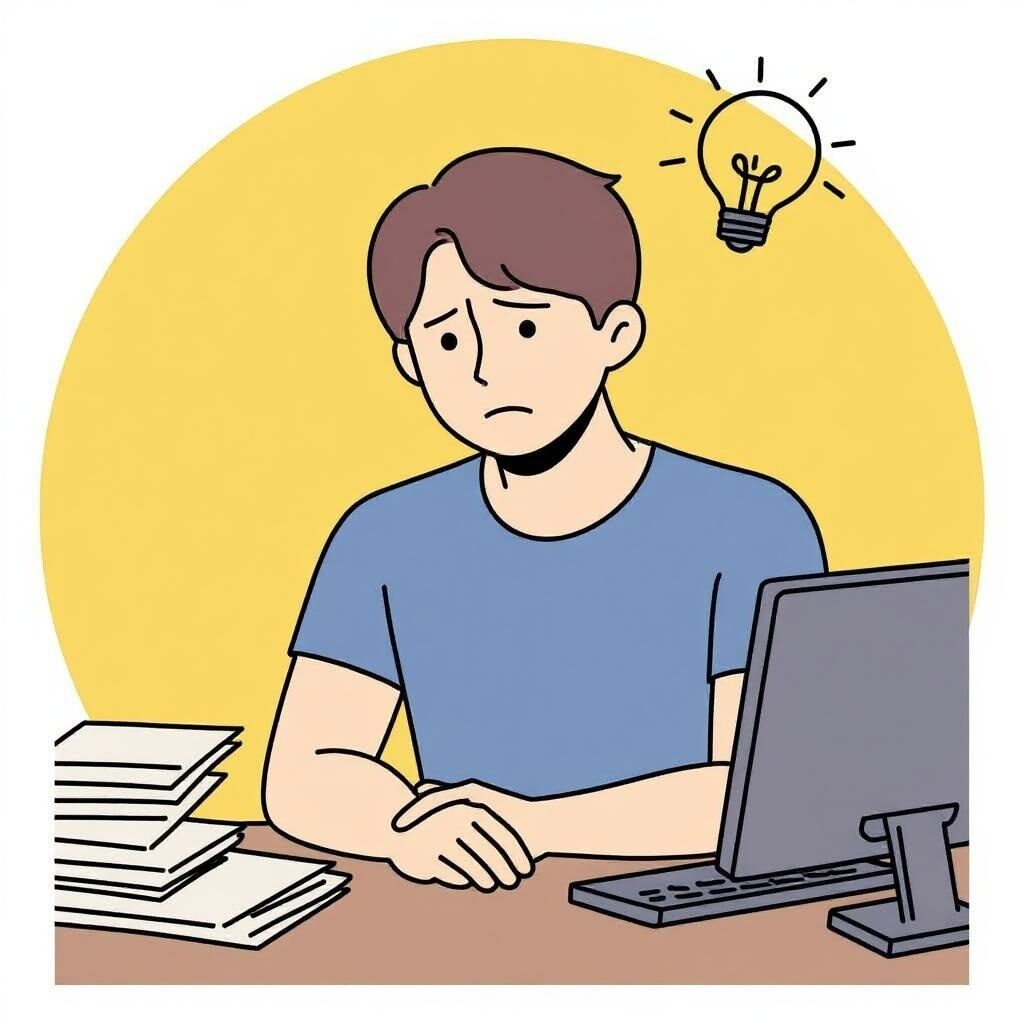
クラウドエンジニアとインフラエンジニアって何が違うの?
どちらを目指すべき?
という疑問をお持ちの方も多いでしょう。実は、この2つの職種には明確な違いがあり、キャリア選択において重要な判断材料となります。転職を検討される前に、ぜひ押さえておきたい3つの違いをご説明します。
関連記事:インフラエンジニアとは?IT初心者でも分かる職種解説

最も大きな違いは、担当するIT環境にあります。
クラウドエンジニアは、AWS、Microsoft Azure、Google Cloud Platform(GCP)などのクラウドサービスを活用して、インターネット上のシステム基盤を設計・構築・運用します。
一方でインフラエンジニアは主に自社で保有する物理サーバーやネットワーク機器を使ったオンプレミス環境を担当することが多い職種です。
オンプレミス環境では、サーバールームに実際に足を運んで機器の交換や設定作業を行う必要がありますが、クラウド環境では全ての作業をリモートで実施できます。この違いにより、働き方や必要なスキルセットが大きく異なってきます。
ただし、近年はインフラエンジニアもクラウド技術の習得が求められるようになっており、従来の境界線は徐々に曖昧になってきています。企業によるDX(デジタルトランスフォーメーション)の推進に伴い、今後数年間はオンプレからクラウドへの移行プロジェクトが多数発生する見込みです。そのため、まずは現場でオンプレミスの知識を実務を通して習得しつつ、並行して独学でクラウド(AWS・Azure)の知識を身につけることを強くお勧めします。
働き方の柔軟性において、クラウドエンジニアは大きなアドバンテージを持っています。クラウド環境は全てインターネット経由でアクセスできるため、場所を選ばずに業務を行うことが可能です。実際に、多くのクラウドエンジニアがフルリモートワークやフレックスタイム制で働いています。
一方、インフラエンジニアは物理的な機器の管理や障害対応のため、オフィスやデータセンターへの出社が必要になる場面が多くあります。緊急時の対応では、深夜や休日でも現地に駆けつける必要があることも珍しくありません。
クラウドエンジニアの場合、システムの監視や運用もリモートで実施でき、自動化ツールを活用することで業務効率も向上します。これらの特徴により、ライフワークバランスを重視する方にとって、クラウドエンジニアは魅力的な選択肢となっています。
年収面
両職種ともに高水準ですが、成長性においてクラウドエンジニアが優位性を示しています。クラウドエンジニアの想定年収は500万円~1,000万円と幅が広く、スキルレベルによって大きく年収を伸ばすことが可能です。特に、リモートワークの普及を背景に、クラウドエンジニアの求人は前年比71%増という驚異的な伸びを記録しています。
一方、インフラエンジニアの平均年収もおおよそ500万円~600万円程度と高水準ですが、オンプレミス環境の需要が徐々に減少傾向にあることから、長期的な成長性においては課題があります。
キャリアパス
クラウドエンジニアは最新技術に触れる機会が多く、DevOps、セキュリティ、データ分析など、幅広い分野への展開が可能です。
また、企業のDX推進が加速する中、IPAの調査では取組企業の割合が2021年の55.8%から2023年の73.7%へと大幅に増加しており、クラウドエンジニアの将来性は非常に高いと言えるでしょう。
これらの違いを踏まえると、柔軟な働き方と高い将来性を求める方には、クラウドエンジニアがおすすめです。一方で、物理的な機器に触れる技術的な興味がある方や、安定した従来型の働き方を好む方には、インフラエンジニアも魅力的な選択肢となります。
実際に、実際にAWS資格取得により年収アップと業務の幅が広がった方の例も参考にしてみてください。


未経験からクラウドエンジニアになりたいけれど、何から学べばいいの?
資格はどの順番で取るべき?
こうした疑問をお持ちの方も多いでしょう。クラウドエンジニアに必要なスキルは多岐にわたりますが、効率的な学習ロードマップを知ることで、最短距離でキャリアチェンジを実現できます。ここでは、優先順位を明確にした実践的な学習プランをご紹介します。
クラウドエンジニアを目指す上で、まず身につけるべきは基礎インフラ知識です。これらの基礎がなければ、クラウド技術を学んでも表面的な理解に留まってしまいます。

Linux基本スキルの習得が第一歩!
クラウドサービスの多くがLinuxベースで動作しており、コマンドライン操作は日常業務で必須です。具体的には、ファイル操作、プロセス管理、権限設定、シェルスクリプトの基本などを習得しましょう。
ネットワーク知識も同様に重要です。TCP/IP、DNS、サブネット、ルーティングなどの基本概念を理解することで、クラウド環境でのネットワーク設計やトラブルシューティングが可能になります。特に、IPアドレスの仕組みやポート番号の概念は、セキュリティ設定においても必要不可欠です。
サーバー知識については、Webサーバー(Apache、Nginx)やデータベース(MySQL、PostgreSQL)の基本的な仕組みを理解しておくことが重要です。これらの知識があることで、クラウド上でアプリケーションを構築する際の設計判断ができるようになります。
これらの基礎スキルを習得するための推奨資格として、LPIC(LinuC)レベル1とCCNAが挙げられます。これらは未経験者が最初に取るべき資格として業界で認識されています。
関連記事:実務で役立つLinuxコマンド一覧完全ガイド
関連記事:CCNAとは?未経験から3ヶ月でITエンジニアを目指す完全ガイド
基礎知識を身につけた後は、クラウド認定資格の取得に進みます。AWS、Microsoft Azure、Google Cloud Platform(GCP)という3大クラウドプラットフォームの中から、どれを選ぶかが重要な判断となります。

初心者に最もおすすめなのはAWS認定資格です。
市場シェアが最も高く、求人数も豊富で、学習教材や情報が充実しているためです。まずは、AWS認定クラウドプラクティショナー(CLF-C01)から始めることをお勧めします。これはAWSの全体像を把握するための入門資格で、技術的な深い知識がなくても取得可能です。
2024年の大幅アップデートによりAWS認定資格は全12種類になりました。最新の技術トレンドに対応した資格が追加されています。これからクラウドエンジニアを目指す人は、各資格の特徴や難易度、キャリアパスとの関連性を理解することで、より戦略的で効果的な資格取得計画を立てることができます。
Azure認定資格
Microsoft製品を多く利用している企業への転職を考えている方におすすめです。Microsoft Certified: Azure Fundamentalsから始めて、Azure Administrator AssociateやAzure Solutions Architect Expertへと段階的にステップアップできます。
GCP認定資格
Googleのエコシステムやデータ分析に興味がある方に適しています。Google Cloud Digital Leaderが入門レベルで、その後Associate Cloud Engineerへと進むのが効率的です。
戦略的な選択基準として、転職を希望する業界や企業の傾向を調べることが重要です。金融業界ではAWSが多く、教育機関ではGoogle Cloud、大企業ではAzureの採用が多い傾向があります。
関連記事:【2025年最新】AWS資格ロードマップ完全ガイド
関連記事:Azure資格ロードマップ|経験・職種別完全ガイド
現代のクラウドエンジニアには、プログラミングスキルが必須となっています。特に、自動化とコード化による効率的な運用が求められており、以下のスキルが重要です。
Shellスクリプト
最も基本的なプログラミングスキルです。サーバーの設定変更、ログ解析、定期的なメンテナンス作業などを自動化するために使用されます。bashやzshの基本的な文法を覚えることで、日常的な作業を大幅に効率化できます。
Python
より複雑な自動化処理やAPI連携、データ処理に使用されます。AWS SDKやAzure SDK、Google Cloud Client Librariesを使用して、クラウドリソースの管理を自動化できます。また、監視システムの構築やログ分析ツールの作成にも活用されています。
Terraform
Infrastructure as Code(IaC)を実現するためのツールです。クラウドインフラの構成をコードで管理することで、再現性や保守性を向上させることができます。HCL(HashiCorp Configuration Language)という専用の記述言語を使用しますが、宣言的な記述方法のため、プログラミング初心者でも理解しやすい特徴があります。
学習の優先順位を明確にし、計画的にスキルアップを進めることで、効率的にキャリアチェンジを実現しましょう。


クラウドエンジニアになりたいけど、何から始めればいいの?
効率的な転職方法を知りたい!
そんな悩みをお持ちの方も多いでしょう。未経験からクラウドエンジニアへの転職は、適切なステップを踏むことで確実に成功に近づけます。IT業界専門の転職エージェントとして実際に支援している実践的なアプローチをご紹介します。
体系的な学習計画の実行
基礎から応用まで段階的にスキルを習得します。まず、Linux基本操作とネットワークの基礎知識を習得し、その後クラウド認定資格の取得を目指します。
効率的な学習方法として、「インプット3:アウトプット7」の比率を意識することが重要です。書籍や動画での学習(インプット)よりも、実際にクラウド環境で手を動かす実践(アウトプット)に多くの時間を割くことで、実務に直結するスキルが身につきます。
学習スケジュールの目安
平日2-3時間、休日5-6時間の学習時間を確保
6-8ヶ月でAWS認定ソリューションアーキテクト – アソシエイトレベルの資格取得を目標
実践的なポートフォリオ作成
学習成果を具体的な成果物として形にします。未経験者のポートフォリオで重要なのは、完璧さよりも「学習プロセスと成長意欲の証明」です。
具体的なポートフォリオ例として、Webアプリケーションのクラウド環境での構築と運用を挙げることができます。例えば、簡単なToDoアプリケーションをAWS上にデプロイし、データベース設計、セキュリティ設定、監視設定、コスト最適化まで一通り実装します。重要なのは、なぜその技術選択をしたのか、どのような課題を解決したのかを説明できることです。

GitHubでのコード管理とREADMEの充実、技術ブログでの学習記録発信も、ポートフォリオの価値を高める重要な要素です。
面接対策
技術面接と人事面接の両方に対応できる準備が必要です。技術面接では、ポートフォリオで使用した技術の詳細説明、なぜその設計にしたのかの理由説明、改善点や今後の拡張案について答えられるよう準備します。
よくある質問例として、「クラウドとオンプレミスの違いは何ですか?」「AWSのEC2とは何ですか?」「なぜクラウドエンジニアになりたいのですか?」などがあります。これらの質問に対して、具体的な事例を交えて説明できるよう準備しましょう。
人事面接では、前職の経験をクラウドエンジニアの業務にどう活かせるかを具体的に説明することが重要です。営業経験があればコミュニケーション能力、事務経験があれば正確性と継続的改善能力など、前職のスキルを技術職にどう転用できるかをアピールします。
企業選びのポイント
未経験者の場合は「教育制度の充実度」を最重要視することをお勧めします。研修期間の長さ、メンター制度の有無、資格取得支援制度、勉強会の開催頻度などを確認しましょう。
また、プロジェクトの多様性も重要な選択基準です。様々な業界のクライアントを持つ企業では、幅広いクラウド技術に触れる機会があり、スキルアップに有利です。企業規模については、大企業では安定性と研修制度、中小企業では裁量権と成長機会というそれぞれのメリットがあります。

これらのステップを着実に実行することで、未経験からでもクラウドエンジニアへの転職成功率を大幅に向上させることができます。重要なのは、各ステップを丁寧に実行し、継続的な学習と実践を心がけることです。
クラウドエンジニアは、DX時代に最も求められるIT職種の一つです。総務省の調査では、日本のパブリッククラウドサービス市場は2023年に3兆1,355億円(前年比25.8%増)に達し、今後も急成長が続くと予測されています。
未経験からでも始められる具体的なステップ
①学習の第一歩:Linux基本操作とネットワークの基礎知識を習得
②クラウド認定資格の取得(実際にクラウド環境で手を動かす)
③実践的なポートフォリオ作成
④企業選び・面接対策
20代という若さは最大の武器です。技術の変化が激しいクラウド分野では、柔軟性と学習意欲こそが成功の鍵となります。今日からでも遅くありません。まずは、学習の第一歩から踏み出してみませんか?
\こんなお悩みをお持ちの方 /
🗣️「先端IT人材になりたい!」
🗣️「転職市場で評価されるスキルを身につけたい」


