
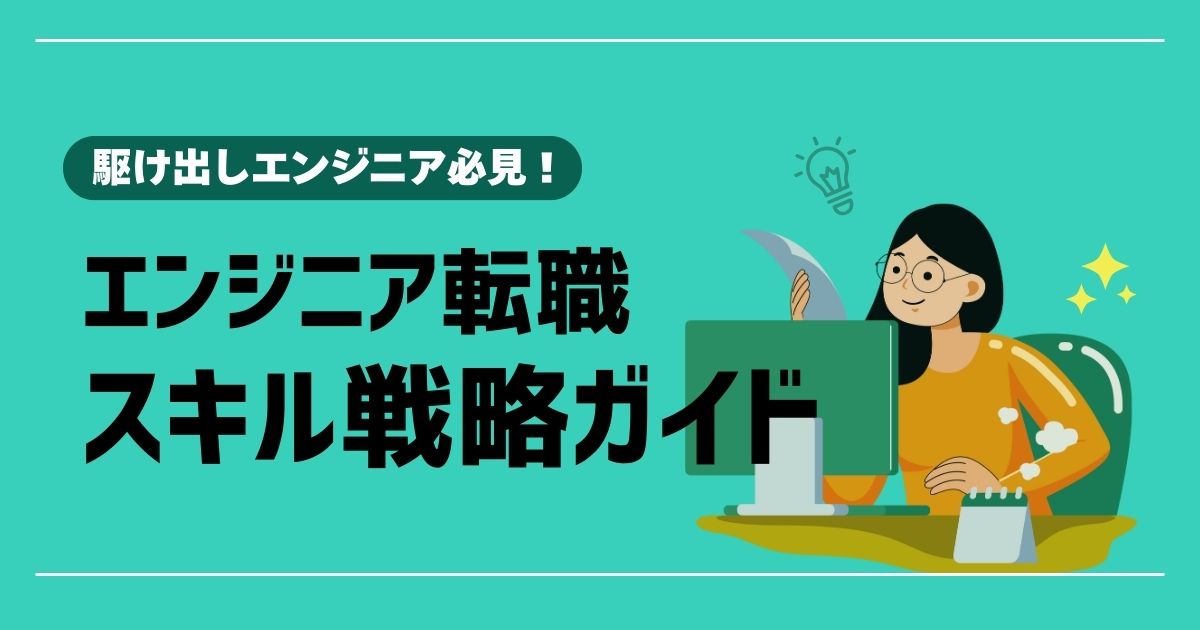
 2025.04.24
2025.04.24

エンジニアとしてのキャリアが始まって間もない1~3年目。経験が浅い中で転職を考えたとき、「自分にはまだスキルが足りないのでは」と不安を抱く方は少なくありません。特に20~30代前半のエンジニアの方からは、「転職面接で技術力を問われたらどう答えたらいいのか分からない」「現職では研修ばかりで実務経験が乏しい」といった声も多く聞かれます。
しかし実は、企業側が求める“スキル”とは、単純な知識量や技術の習得状況だけではないのです。この章では、駆け出しエンジニアが転職の面接でつまずきやすい「スキル不足」というテーマについて、その誤解と真実を紐解いていきます。
転職面接で頻出する質問のひとつに、「どんな技術を使ってきましたか?」「できること・できないことは?」といった、スキルに関するものがあります。このとき多くのエンジニアが「完璧に使いこなせる技術がない」「答えられる実績が乏しい」と感じ、うまくアピールできずに終わってしまいます。
ですが、企業が本当に見たいのは、“現時点の完成されたスキルセット”ではなく、「どんな姿勢で学び、どこまで実践してきたのか」「習得した知識をどう業務に応用しているのか」といった“成長の過程”です。つまり「学ぶ力」「応用力」「現場理解力」など、ポテンシャルを含めた広い意味でのスキルが問われているのです。
たとえば、ある企業では、「AWSは使ったことがありませんが、Linux環境でサーバ構築の流れは経験しました」といったエピソードが、逆にポジティブに受け止められたというケースもあります。重要なのは、経験の“量”より“質”、そしてそこから得た“学び”をどう言語化できるか、という視点なのです。
「転職には実務経験が必要」「スキルがないと書類すら通らない」——そんな声を聞いたことがあるかもしれません。でも実際には、企業がエンジニアに求めるのは「コードが書ける人」だけではありません。技術力だけでなく、チームで働く力や、課題解決のための姿勢、柔軟性や学び続ける力など、総合的なビジネススキルも強く求められているのです。
たとえば、経済産業省の「IT人材白書(2023年版)」によると、若手IT人材に企業が期待する力として、「論理的思考力」「主体性」「コミュニケーション能力」が技術スキル以上に挙げられているケースもありました(※出典:経済産業省 IT人材白書2023)。
このことからも分かるように、たとえ現時点で特定の技術スキルが不足していたとしても、「チームでの開発経験」「報連相の徹底」「積極的にドキュメント整備を提案した経験」などがあれば、企業にとっては十分に評価対象となります。むしろ、技術スキルばかりに目を奪われ、こうした“ヒューマンスキル”を軽視してしまうと、思わぬ形で選考から外れてしまうこともあるのです。
駆け出しエンジニアが転職活動でつまずく背景には、いくつかの共通パターンがあります。中でも代表的なものを3つ、ご紹介しましょう。
1つ目は、「実務経験がないから」と応募をあきらめてしまうパターン。これは非常にもったいないケースです。たとえ業務経験が乏しくても、個人開発や学習履歴、GitHubやQiitaでのアウトプットなどをきちんと整理すれば、スキルの証明材料になります。「経験がないから無理」と決めつけず、まずは“見せ方”を工夫してみましょう。
2つ目は、スキルだけで選考に臨んでしまうパターン。技術スタックだけに注目して企業選びをすると、「人間関係」「開発体制」「育成環境」などが自分に合わず、早期離職につながるリスクがあります。自分の“働き方”にフィットした環境を選ぶ視点も大切です。
そして3つ目は、「志望動機が薄い・浅い」パターン。これは実は、スキル不足以上に面接でマイナス評価を受けやすいポイントです。「なぜこの企業なのか」「どう成長したいのか」というストーリーが弱いと、いくらポテンシャルがあっても採用には至りません。企業研究と自己分析を丁寧に行い、“想い”を言葉にできる準備をしておきましょう。

「スキルに自信がない」「自分みたいなレベルで転職できるのだろうか」と不安になる方は少なくありません。特に、経験が1〜3年ほどの駆け出しエンジニアにとって、スキル不足は転職活動の大きなハードルに感じられがちです。しかし、実際のところ“スキルの完璧さ”よりも、“見せ方”や“戦略”で転職成功の可能性は大きく変わります。
ここでは、スキル不足でもチャンスを掴める5つの現実的な対策をご紹介します。読み進めることで、自分にできることが見えてくるはずです。
まず大切なのは、「自分にどんなスキルがあるか」を整理することです。多くの駆け出しエンジニアは、「自分はまだスキルがない」と思い込んでいますが、実際には現場で積んだ経験や身についた知識は立派なスキルの一部です。
おすすめは、「STARフレームワーク」を使って、自分の経験をストーリー形式で棚卸しする方法です。
この流れに沿って書き出すことで、抽象的な経験が「伝わるスキル」に変わります。また、業務で触れてきたツール(例:Linux、MySQL、Git など)や開発フロー、保守対応の経験なども忘れずに洗い出しましょう。
「自分のスキルを証明する方法がわからない」という人にこそ活用してほしいのが、GitHubやQiitaなどのアウトプット系プラットフォームです。特に経験が浅いエンジニアにとって、実績を“見える化”できるこれらのサービスは強力な武器になります。
GitHubでは、コードの品質やコミット履歴、設計の意図などを通じて「自走力」や「思考プロセス」をアピールできます。Qiitaでは、エラー対応や学習ログを記事にまとめることで、「学び続ける姿勢」や「情報整理力」を伝えられます。
現場では、コードのスキルそのものよりも、「どうやって学び、改善してきたか」に注目する企業も多いため、たとえ完成度が低くてもアウトプットは積極的に行うのが効果的です。
「毎日忙しくて学習時間がとれない…」そんな方でも継続できる学習法があります。ポイントは、“短時間でも効率よく学べる環境を整えること”です。
おすすめは次の3つです。
小さな積み重ねが、スキルアップと自己PR力の両方に繋がっていきます。
技術力だけで評価されるわけではないのが、ITエンジニアという職種の面白さでもあります。特にチーム開発が基本となる現場では、「人と関わる力」や「課題に対して前向きに取り組む姿勢」も評価ポイントになります。
たとえば、こんな強みも武器になります。
こうした“技術以外の力”を具体的なエピソードとして語ることで、企業に「この人は一緒に働きたい」と思ってもらえる可能性が高まります。
最後にご紹介するのは、転職エージェントの活用です。自力で求人を探すのももちろん可能ですが、スキルに不安がある段階では、「どの求人なら自分に合っているか」をプロと一緒に考える方が効率的です。
エージェントは、あなたの経験やスキル、希望条件を元に、「スキルよりポテンシャル重視」の企業を選定してくれたり、書類作成や面接対策でスキルの見せ方をアドバイスしてくれたりします。
スキル不足を補うための“戦略的な武器”として、エージェントの活用も視野に入れてみましょう。

転職市場において、年齢や経験年数は大きな意味を持ちます。とくにITエンジニアとしてのキャリアが浅い20代〜30代前半では、「スキルが足りない」と感じて不安になる方も多いでしょう。しかし、スキルが十分でないからといって、転職で不利になるとは限りません。むしろ、自分の状況に合った戦略を取れば、「スキル不足=不利」とはならないのです。
ここでは、年齢や経験別に分けて、駆け出しエンジニアが転職で“戦えるスキル戦略”をご紹介します。
20代前半で、IT業界に入ったばかりの方や、職歴のほとんどが非IT職という方は、「転職できるだけのスキルがない」と悩むことが多いです。でもご安心ください。この段階で企業が求めているのは、“完璧なエンジニア”ではなく、“ポテンシャルと素直さ”です。
では、未経験に近い方がまず何から学ぶべきかというと、最優先は「業務で使われる基礎技術」の習得です。たとえば以下のようなスキルは、多くの現場で求められる共通項です。
これらは「Progate」や「ドットインストール」などのオンライン学習サービスで、短期間でも効率的に身につけることができます。さらに、自主制作のポートフォリオや、技術ブログでのアウトプットを加えることで、「学び続ける姿勢」や「自走力」が企業に伝わりやすくなります。
このフェーズで最も重要なのは、スキルの“深さ”より“土台の広さ”です。基礎をしっかり固めておくことで、実務に入ってからの吸収スピードも格段に上がります。
20代後半のエンジニアにとっての転職は、いわば“伸びしろ”と“成果”のバランスが問われるタイミングです。「実務経験はあるけど、目立った実績がない」「スキルが浅いままで大丈夫か」と不安になる方も多いですが、実はこの層こそ転職市場では重宝されています。
その理由は、一定の現場経験がありながらも、柔軟に学びを続けられるポテンシャルがあるからです。ここで重要なのは、職務内容を「単なる作業の羅列」で終わらせず、「どんな課題に向き合い、どう工夫して取り組んだか」を伝えること。たとえば「仕様書が不明確な中でも、要件整理のMTGを提案し、納期に間に合わせた」など、日常業務の中の行動が“強み”として評価されます。
また、使用していた言語やツール(Java、PHP、React、Docker、CI/CDなど)を具体的に記載しつつ、それをどう活用していたのかも補足しましょう。企業は「スキルの羅列」ではなく、「実務との結びつき」を見ています。
30代に差し掛かると、転職活動においては「キャリアの方向性」がよりシビアに問われるようになります。「なんとなくスキルを広げてきたけれど、自分が何者なのか分からない」という声も少なくありません。この段階で転職を成功させるには、これまでの経験を棚卸しし、「自分のキャリアの軸」を言語化することが必須です。
たとえば、開発よりもプロジェクト推進や顧客折衝にやりがいを感じてきたなら、PL(プロジェクトリーダー)やPM(プロジェクトマネージャー)候補の求人に目を向けるのも一つの手です。あるいは、クラウドやセキュリティなど今後需要が伸びる領域で専門性を高めたいなら、AzureやAWS認定資格を活かせるポジションへの転職が視野に入ってきます。
30代前半は、未経験分野にチャレンジするラストチャンスとも言われています。だからこそ、「自分が何を大事にしたいか」「どんな働き方をしたいのか」といった価値観の整理が、転職成功の鍵を握ります。
もし具体的なキャリアの軸を整理したいと感じたら、こちらの記事でさらに詳細なポイントをご覧ください。
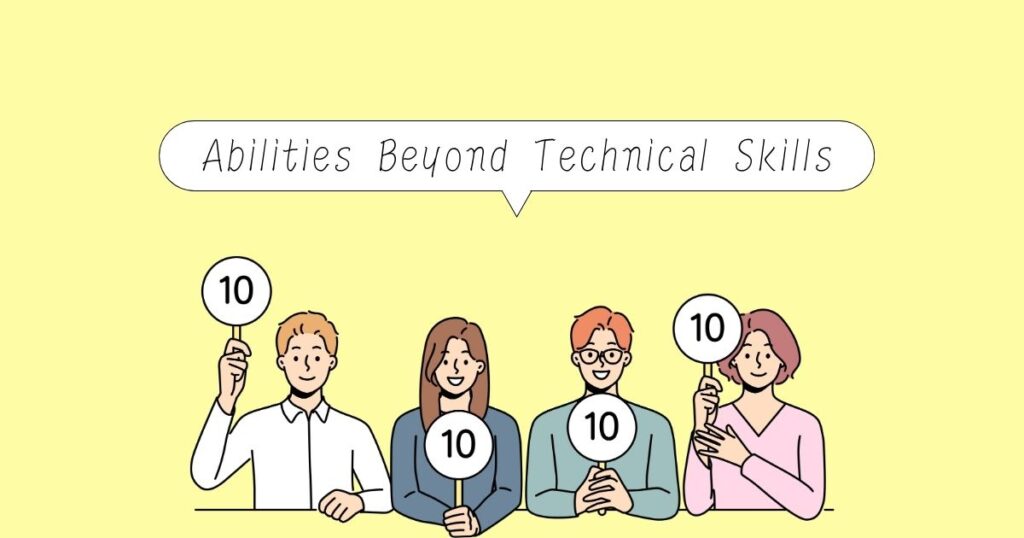
ITエンジニアとして転職を考えたとき、多くの方が気にするのが「自分の技術力は通用するのか?」という点です。しかし、実は企業が採用の判断材料として重視しているのは、技術スキルだけではありません。とくに1〜3年目の駆け出しエンジニアの場合、「今できること」よりも「これからの伸びしろ」や「チームで働く素養」に注目している企業が多いのが現実です。
この章では、スキルに自信がない方でも転職活動を有利に進められるよう、「技術以外で評価される力」について具体的に解説します。
「エンジニアは技術がすべて」と思われがちですが、企業が高く評価するのは“コミュニケーション力”も同じくらい重要なスキルです。特に現場では、進捗報告や課題の共有など「報連相(報告・連絡・相談)」が円滑にできることが、プロジェクト成功のカギを握ります。
たとえば、実装中に仕様と合わない点があれば、すぐに相談できるか。タスクの優先順位が変わったとき、チームに適切に共有できるか。このような“当たり前のこと”をしっかりこなせる人材は、実は非常に貴重なのです。
さらに、リモートワークの普及により、チャットやドキュメントでのやりとりが中心になった今、文章でのコミュニケーション能力も求められています。技術スキルと同じくらい「伝える力」は重要だという意識を持ちましょう。
もう一つ、企業がスキル以上に重視しているのが「問題解決の思考力」です。エラーが発生したときにどう原因を切り分けるか、予期しない事態にどう対処するか。これらは教科書では学べない“現場力”であり、採用面接でもよく問われるポイントです。
例えば、「どのログを見て、どう仮説を立てて、どう検証したのか」といった過程を具体的に語れる人は、それだけで説得力があります。また、チーム内での役割や、誰に相談したか、どういう改善提案をしたかまで話せると、より評価が高まります。
転職活動では、成功体験よりも「失敗から何を学んだか」を語れるほうが、成長意欲や柔軟性をアピールできます。問題発生時の動き方を、自分の“強み”として伝えてみましょう。
スキルに自信がなくても、「成長意欲があるか」は必ず評価されます。特に駆け出しエンジニアであれば、完璧な技術よりも、“今後伸びる人材か”という観点で見られるため、学び続ける姿勢をどれだけ具体的に伝えられるかがカギになります。
例えば、「UdemyでReactの講座を月2本ペースで受講しています」「Qiitaで週1回、学習内容をまとめています」といった行動ベースの情報があると、説得力が格段に上がります。また、社外勉強会への参加や、技術イベントでの登壇経験なども強いアピール材料になります。
このような努力は、エンジニアとしての地力を示すだけでなく、「環境に依存せず、自走できる人材」として企業からも高評価につながります。
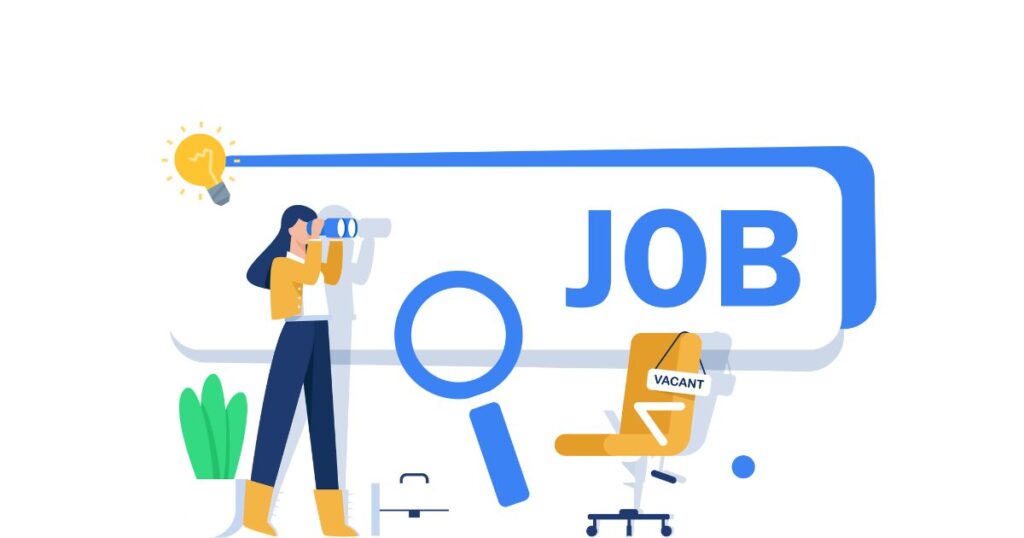
「今の自分のスキルで、ほんとうに転職できるのかな…?」
これは、駆け出しエンジニアの多くが一度は抱く不安です。でもご安心ください。実は「スキル不足」に見える状態でも、十分に採用されやすい企業はたくさん存在します。
この章では、「ポテンシャル採用」を掲げる企業の見つけ方から、教育制度・求人票の見極め方、そして今注目される“DX推進企業”が求める人物像まで、スキルに自信がなくても転職を成功に導ける企業の見極め方を詳しくご紹介します。
ポテンシャル採用とは、現時点でのスキルよりも「今後の成長性」や「学習意欲」を重視して人材を採用するスタイルのことです。20代の駆け出しエンジニアにとっては、この考え方を取り入れている企業こそが狙い目です。
ポテンシャル採用を行っている企業には、いくつか共通する特徴があります。たとえば…
こうした企業は、スキルよりも“伸びしろ”を評価してくれる傾向があります。探し方としては、「ポテンシャル採用 エンジニア」「未経験 エンジニア 転職」などのキーワードで転職サイトを検索するのが有効です。
仮にポテンシャル採用で入社できたとしても、入社後の成長環境が整っていなければ意味がありません。そこで重要なのが、企業の「教育制度」や「育成体制」を事前に見極めることです。
注目すべきチェックポイントは以下の通りです。
実際、経済産業省の調査(「IT人材白書2020」)でも、企業の人材育成体制が整っていることが若手定着率の向上に直結するという結果が出ています。教育制度の充実度は、その企業の“本気度”を映し出す鏡でもあるのです。
「第二新卒歓迎」や「微経験OK」という言葉が求人票にあると、つい安心してしまいがちですが、注意すべきポイントもあります。これらの表現が使われているからといって、すべての求人が初心者に優しいとは限りません。
見極めるポイントは以下のような点です。
また、企業の口コミサイトやSNSなどで実際の声をリサーチするのも効果的です。実際にその企業で働いている人の声は、求人票には現れないリアルな情報源になります。
現在、多くの企業が「DX(デジタルトランスフォーメーション)」の推進に力を入れています。経済産業省も「2025年の崖」問題として、DX人材の不足を深刻に捉えており、若手エンジニアへの需要は年々高まっています。
DXを進める企業は、既存のシステムを変革し、新しい技術や仕組みを導入する必要があるため、「変化に柔軟に対応できる若手人材」を強く求めています。
そして、多くのDX推進企業では、技術スキルの高さよりも「吸収力」「学ぶ姿勢」「コミュニケーション力」が重視される傾向があります。
さらに、DX領域ではクラウド技術(AWS、GCPなど)やSaaSツール(Slack、Notionなど)に触れられる機会が多く、スキルアップにも直結します。
これからの時代にマッチした働き方・学び方を求めるなら、こうした企業はまさに“狙い目”と言えるでしょう。

転職を考える際、スキル不足が不安になるのは自然なことですが、それを恐れて転職を諦める必要はありません。重要なのは「自分の強みを正しく伝えること」と「学び続ける姿勢をアピールすること」です。ポートフォリオや実務経験を活用し、スキルを証明する方法をしっかり準備しましょう。
また、年齢や経験に応じた戦略を立てることも大切です。20代であれば基礎を固め、30代ではキャリアの方向性を明確にすることで、転職を有利に進められます。スキルだけでなく、コミュニケーション能力や思考力も評価されるため、それらを意識的にアピールすることがポイントです。
最後に、スキル不足を感じても、ポテンシャル採用や育成体制が整った企業を選べば、自信を持って転職活動を進められるでしょう。転職は戦略的に行えば、必ず成功に繋がります。


