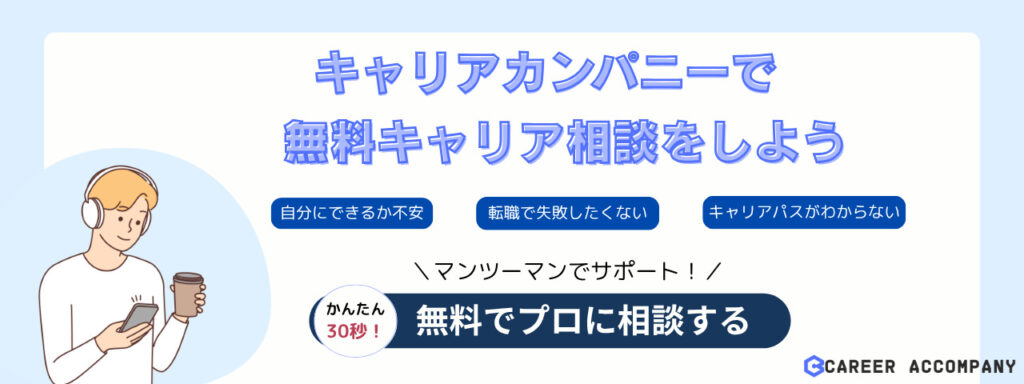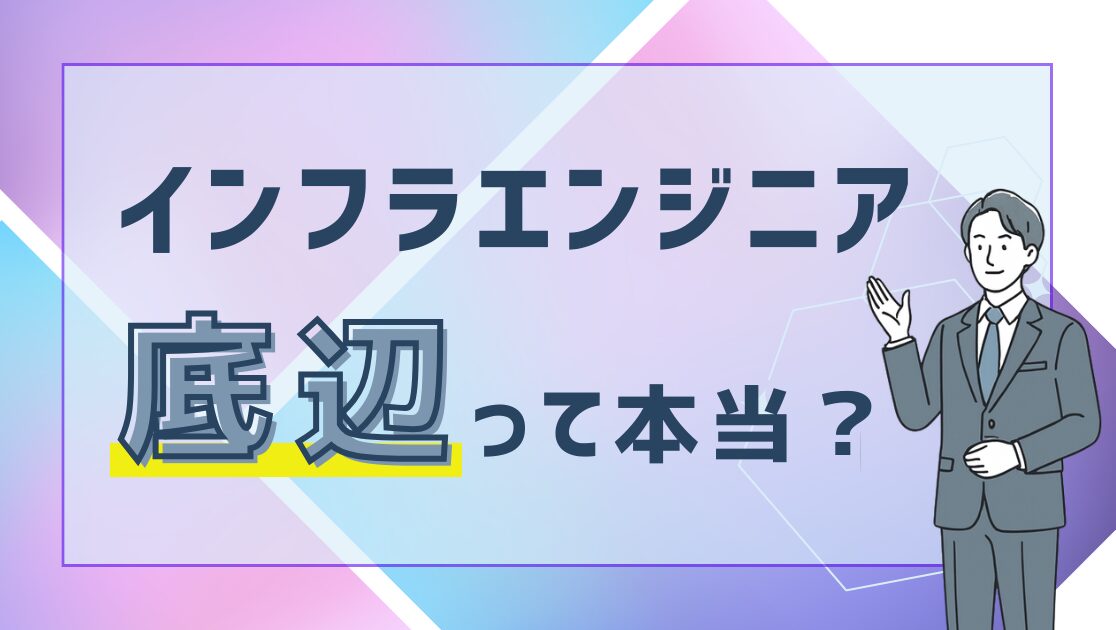
あなたは、ネットやSNSで「インフラエンジニアは底辺」という書き込みを見て、自分の仕事に価値がないと感じているかもしれません。年収290万円の給与明細を見て、「このままでいいのか」と不安になっているかもしれません。
でも、大丈夫です。あなたは決して「底辺」なんかじゃありません。
この記事では、転職エージェントとして数百人のインフラエンジニアを支援してきた経験から、「底辺」という誤解を解き、年収500万円を実現するための具体的な方法をお伝えします。
関連記事:システム運用保守が「きつい」あなたへ|年収アップを実現する脱出ロードマップ


まず最初に、あなたの心に刺さった「底辺」という言葉について、しっかりとお話しさせてください。
SNSやネットで目にする「底辺」という言葉、あれは本当に根拠のないただの偏見なんです。
「年収290万円なんて底辺だ」と落ち込んでいませんか?でも、ちょっと待ってください。国税庁の「令和5年分民間給与実態統計調査」を見ると、20代の平均年収は316万円~353万円なんです。あなたの年収が290万円なら、確かに平均より少し低いかもしれません。でも「底辺」なんて言われるほど異常な数字じゃないんですよ。
それに、インフラエンジニア全体で見れば、平均年収は443万円もあるんです。つまり、今は低くても、経験を積めばちゃんと上がっていく職種なんです。

運用保守なんて誰でもできる仕事でしょ?
って思っていませんか?実はそれ、大きな誤解なんです。
経済産業省の「IT人材需給に関する調査」によると、2025年には最大43万人ものIT人材が足りなくなるって言われているんです。特に、インフラ領域の人材が圧倒的に不足しています。
さらに、「2025年の崖」と呼ばれる問題では、レガシーシステム(老朽化した古いシステム)の維持・移行に対応できる人材が圧倒的に不足しており、年間最大12兆円もの経済損失が出るかもしれないと言われています。
つまり、オンプレミス環境で運用保守をやってきたあなたのような人材こそ、今後ますます必要とされるんです。採用現場でも「クラウドの知識より、障害対応をやり切った経験が欲しい」という企業、実は結構多いんですよ。
「インフラエンジニアって地味だし、評価されないよね」と感じていませんか?
でも考えてみてください。あなたが夜勤で監視している間、何百万人もの人が安心して銀行のATMを使えています。病院の電子カルテが動いています。ECサイトで買い物ができています。これらのシステムが安定して動き続けているということは、あなたが確実に仕事をしている証拠なんです。
あなたが守っているシステムの安定稼働は、企業の信頼そのものなんですよ。
地味かもしれません。でも、社会を裏側から支える、なくてはならない仕事。それがインフラエンジニアなんです。

さて、ここまで「あなたは底辺じゃない」ってお伝えしてきました。でも、「じゃあなんで『底辺』って言われるの?」って疑問が残りますよね。
この章では、インフラエンジニア、特に運用保守が「底辺」と誤解される4つの構造的理由を解説します。
インフラエンジニアが「底辺」と呼ばれる最大の理由は、多重下請け構造にあります。
例えば、あるプロジェクトで、お客さんが元請け企業に月80万円払っているとします。でもそれが二次請け、三次請けと流れていくうちに、実際に働くあなたの手元に来るのは20万円(手取り16万円くらい)なんてことが本当にあるんです。

つまり、あなたの仕事の価値は80万円なのに、受け取れるのは4分の1だけなのです。あなたの年収が低いのは、能力の問題じゃないんです。所属している会社の立ち位置の問題なんですよ。

運用保守なんて誰でもできる
マニュアル通りに動くだけでしょ
こういう声、聞いたことありませんか?
でも実際は全然違いますよね。システムが落ちた時、マニュアル通りになんて絶対いきません。状況を見て判断して、お客さんに説明して、ベンダーと調整して…本当に大変な仕事です。
採用現場では「障害対応をやり抜いた経験が欲しい」という企業が、増えています。なぜかというと、クラウドの知識は数ヶ月で身につくけど、トラブルの時に冷静に判断する力は、実務経験でしか身につかないからです。
ただ、運用保守の成果って「システムが止まらなかった」という”何も起きなかった”状態なので、評価されにくいんですよね。これが偏見を生んでいる大きな理由です。
IT業界には、なんとなく「設計や開発の方が上、運用保守は下」みたいな雰囲気がありますよね。
でも、実際のプロジェクトでは、運用保守の経験がない設計は、トラブルに弱いシステムを作ってしまうことが多いんです。「こう設計すれば障害が起きにくい」「この監視をしておけば早期発見できる」。こういう知見は、運用保守の現場でしか得られません。
最近、「設計チームに運用保守経験者を入れたい」という企業からの相談、すごく増えてるんですよ。つまり、運用保守経験は、キャリアアップのための強力な武器になるんです。
「夜勤ばっかりできつい」「監視画面見てるだけで単調」。確かにこういう面はありますよね。
でも、運用保守の仕事って本当は幅広いんです。障害対応、キャパシティ管理、セキュリティパッチの適用、ベンダー調整、ドキュメント作成…いろいろあります。
それに、実は社内SEや情報システム部門の運用保守は、夜勤がほぼゼロなんですよ。クラウド環境の運用保守では、自動化ツールを使いこなすスキルが求められて、全然単調じゃありません。
「運用保守=夜勤・単調」というイメージは、一部の事実だけが大げさに伝わっているんです。
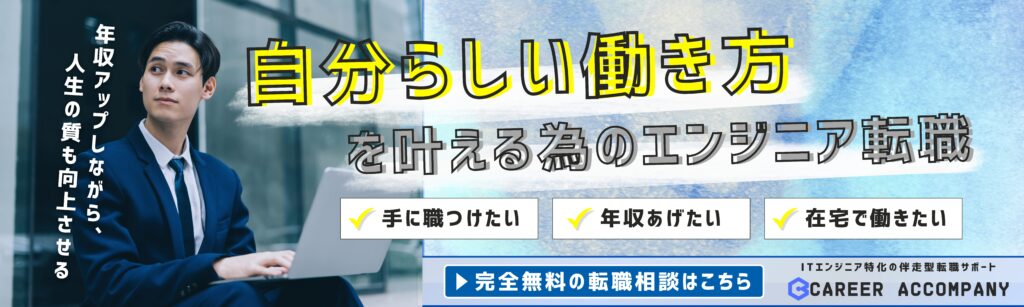

「底辺」という言葉に苦しんでいるあなたに、最も必要なのは「希望」です。ここでは、転職エージェントとして実際に支援した3名の成功事例をご紹介します。全員が運用保守からスタートし、年収290-350万円という状況から脱出しました。彼らの共通点は、「今の経験を武器にして、次のステップに進んだ」ことです。
Aさん(26歳・男性)
Aさんは、夜勤の待機時間にAWSの勉強を始めました。AWS無料アカウントで実際に手を動かして、3ヶ月で「AWS認定ソリューションアーキテクト – アソシエイト」を取得。個人でEC2やS3を使った簡単なWebサイトを作ってGitHubに公開しました。
面接では「障害対応の経験」と「AWSの実践スキル」を組み合わせてアピール。見事内定を獲得しました。
実は、AWS資格保有者の53%が年収600万円以上なんです。運用保守経験+クラウド資格の組み合わせ、本当に強いんですよ。
Bさん(28歳・女性)
Bさんは「夜勤のない働き方」を最優先に転職活動を進めました。社内SEは、事業会社の情報システム部門で働くポジションで、夜勤ほぼゼロ、残業も少なめが特徴です。
面接では「ユーザーとの調整力」と「ベンダー管理の経験」を強調。運用保守で培った「トラブル時の報告・調整力」は、社内SEで最も求められるスキルなんです。
働き方を重視するなら、社内SEはすごくおすすめです。
Cさん(29歳・男性)
Cさんは、ネットワーク運用で触っていた「ファイアウォールやIDS/IPSの知識」を武器に、セキュリティ領域へ転身しました。
まず「情報処理安全確保支援士」を取得(6ヶ月)を取得。セキュリティエンジニアの平均年収は511万円と高水準で、採用企業からは「セキュリティ人材が圧倒的に足りない」という声をいつも聞きます。
運用保守でセキュリティ機器を触った経験があれば、セキュリティエンジニアへの転身は十分可能なんです。
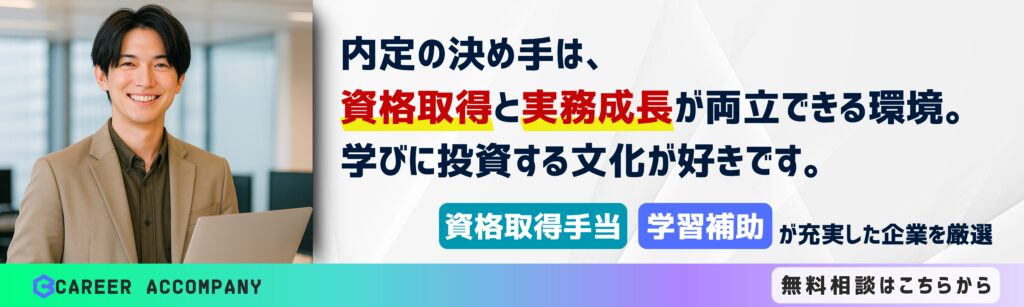

ここまで、「あなたは底辺ではない」という事実と、実際に年収を上げた成功事例をお伝えしてきました。この章では、あなたが今日から始められる、年収500万円を実現するための最短ロードマップを4つのステップで解説します。
まず最初にやることは、今あなたが持っているスキルを書き出すことです。
「自分には何もない」って思ってませんか?それ、違いますよ。運用保守の仕事の中で、あなたは既にたくさんのスキルを身につけているんです。
紙かスマホのメモアプリに、こんなことを書き出してみてください。
スキル例
これ全部、企業が求めているスキルなんです。特に障害対応の経験は、採用現場ですごく評価されます。教科書通りにいかない状況で冷静に判断する力、これって本当に貴重なんです。
棚卸しができたら、「どのスキルを伸ばすか」を考えましょう。今の経験を活かせる方向を選ぶのがポイントです。
スキルの棚卸しが終わったら、次は資格取得です。
「資格なんて意味ない」って声もありますが、転職市場では資格は客観的な証明としてすごく大事なんです。特に、運用保守から転職する時は、「構築経験がない」というハンデを資格で補えるんですよ。
おすすめ資格の優先順位
1位:AWS認定ソリューションアーキテクト – アソシエイト(勉強期間3-6ヶ月、受験料15,000円)
2位:CCNA(勉強期間3-6ヶ月、受験料36,960円)
3位:LinuC Level 2 / LPIC Level 2(勉強期間3-6ヶ月)
資格は、あなたの本気度を証明する武器になります。
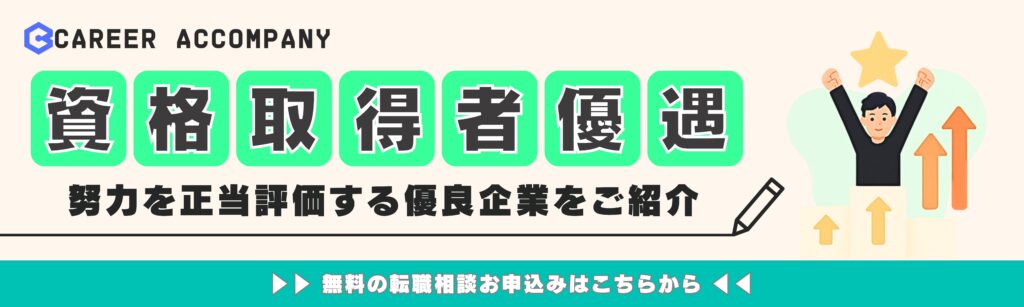
資格を取ったら、いよいよ転職活動です。ここで大事なのは、転職エージェントを使うこと。年収交渉や面接対策のサポートが受けられます。
転職活動の流れ
面接で大事なのは、「運用保守経験をどう強みに変えるか」です。
例えば、「障害対応を年間50件経験して、平均復旧時間を30分短縮した」「監視ツールの改善提案で、誤検知を20%減らした」みたいに、具体的な数字を使ってアピールするのがポイントです。
「システムを止めなかった実績」、これは採用企業が一番重視するポイントです。
「何から始めればいいかわからない」というあなたに、今日から始められる3つのアクションをお伝えします。
1. AWS無料アカウントの作成(10分)
AWS公式サイトにアクセスして、無料アカウントを作ってみてください。1年間無料でEC2やS3が使えます。まずは触ってみることが大事です。
2. 転職エージェントへの登録(15分)
登録するだけで、あなたの市場価値が分かります。「自分は本当に底辺なのか?」という不安、客観的なデータで解消できますよ。
3. LinkedInプロフィールの作成(20分)
経歴を登録すると、スカウトが届き始めます。実際、LinkedInから年収100万円アップした人、たくさんいるんですよ。
この3つを今日中に終わらせれば、明日のあなたは確実に昨日より前進しています。

「インフラエンジニアはもう終わり」「AIに仕事を奪われる」。こんな声を聞いて、不安になってませんか?
でも安心してください。IT人材は、2025年まで に最大43万人不足するんです。特にインフラ領域の需要は、拡大しています。
DX(デジタルトランスフォーメーション)の波で、インフラエンジニアの活躍の場は広がってるんです。
クラウドインフラ設計
オンプレからクラウドへの移行プロジェクトは今後10年続きます。オンプレ経験者は引く手あまたで、AWS資格保有者の平均年収は628万円です。
セキュリティ基盤構築
サイバー攻撃の高度化で、セキュリティ人材が圧倒的に不足。平均年収は511万円と高水準です。
DevOpsエンジニア
開発と運用をつなぐ役割で、年収600万円以上の求人が中心です。
これら3領域、全部「運用保守経験」を活かすことができます。
「オンプレがなくなったら、自分の仕事もなくなる」って心配してませんか?
実は違うんです。総務省の「令和5年版情報通信白書」によると、企業の73.5%がクラウドを使ってますが、これは「オンプレの置き換え」じゃなくて「併用」なんです。
つまり、オンプレとクラウド両方を理解できる人材の価値が上がってるんです。実際、「オンプレ→クラウド移行経験者」の求人単価、月80万円超えることもあるんです。
対策は、今のオンプレ知識を武器にしながら、AWSやAzureの基礎資格を取ること。オンプレで培った知識は、クラウドでも90%以上応用できます。無駄になんてなりません。
「ChatGPTがコード書く時代に、自分の仕事は大丈夫?」って不安ですよね。
でも、AIは「作業の自動化」はできても、「判断と責任」は代替できないんです。
これら全部、人間にしかできない仕事なんです。採用企業も「AIは道具。それを使いこなす人材が価値を持つ」って認識をしています。
「35歳転職限界説」って聞いたことありますか?でも、インフラエンジニアには当てはまらないんです。
35歳以降の3つのキャリアパターン
スペシャリスト路線
特定技術を極めて年収800万円以上。40代でセキュリティアーキテクトとして年収1,000万円超える人もいます。
マネジメント路線
運用チームのリーダーやプロジェクトマネージャーに。実務経験のあるマネージャーが不足してるので、35歳以降がチャンスです。
社内SE路線
夜勤ゼロ・残業少なめ。年収450-600万円で、ワークライフバランス重視の人に最適。
35歳を過ぎても、選択肢はたくさんあります。どれを選ぶかは、あなた次第です。
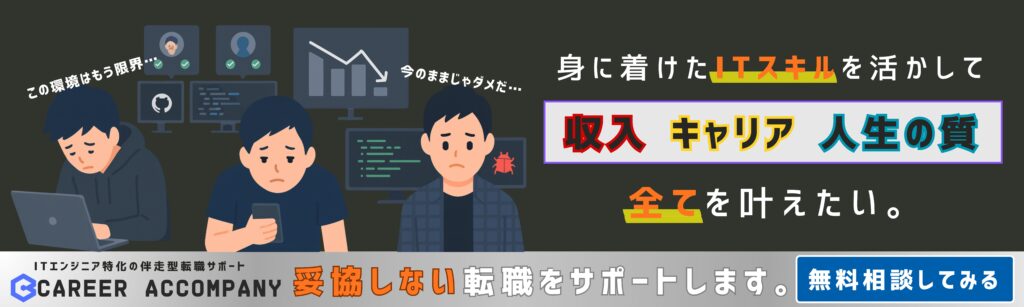
ここまで読んでいただき、ありがとうございます。もう大丈夫です。この記事で見てきた通り、あなたは決して「底辺」なんかじゃありません。
年収の低さに悩んでいる今の状況は、多重下請け構造という業界の歪みが原因で、あなたの能力とは全く関係ありません。
2025年には43万人のIT人材が不足します。AWS資格を取れば年収600万円以上が現実的。セキュリティやクラウドに進めば、年収500万円は十分狙えます。
AWS無料アカウントの作成、転職エージェントへの登録、LinkedInプロフィールの作成。この3つ、今日中にできますよね。
明日のあなたは、今日のあなたより確実に前に進んでいます。
最後に、転職エージェントとして何百人ものインフラエンジニアを支援してきて思うことがあります。「底辺」と感じ悩んでいる人ほど、その後の成長が早いんです。なぜなら、現状に危機感を持って、変わろうとする意志があるから。
あなたはもう、変わるための第一歩を踏み出してます。自信を持って、次の一歩を進めてください。応援してます。